 |
 |
大正10(1921)年4月15日、本校の前身である共愛裁縫女学校が、姫路市光源寺前に設立されました。摺河静男が校祖として学園運営を担い、静男の妻ウメが初代校長に就きました。明治から大正にかけて義務教育が普及し、大正デモクラシーの風潮のもとで自由教育運動が広まるなか、大きな期待が寄せられました。
大正11年3月に南畝町に移転、昭和7年3月には現在地である豊沢に新校舎と寄宿舎が落成し、本校はその後の発展の基礎を築いていきました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
二人三脚でのスタート
(校祖 摺河静男・校母 摺河ウメ)
|
 |
姫路市南畝町の校舎
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 自転車で登校する生徒たち
|
 |
姫路市豊沢に新築された 新校舎と寄宿舎
|
|
 |
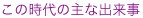 |
 |
| 大正10年 |
 |
創立者摺河静男、姫路市光源寺前に共愛裁縫女学校を設立(本科・実科・研究科・高等部) |
| 大正11年 |
 |
校舎を新築し、姫路市南畝町に移転 |
| 大正15年 |
 |
大正天皇崩御、「昭和」と改元 |
| 昭和 2年 |
 |
金融恐慌
甲種実業学校として姫路女子職業学校を設立(本科・師範科・家政科・高等研究科)
姫路高等女子職業学校と改称
|
| 昭和 4年 |
 |
共愛裁縫女学校を廃止 |
| 昭和 6年 |
 |
甲種女子商業を併設(商業本科)
満州事変
|
| 昭和 7年 |
 |
姫路市豊沢に新校舎、寄宿舎落成 |
| 昭和12年 |
 |
盧溝橋事件(日中戦争勃発) |
|
 |
 |
 |
共愛裁縫女学校
|
| |
大正11年度3月 |
 |
17名 |
 |
| 大正11年度7月 |
 |
4名 |
| 大正12年度 |
 |
50名 |
| 大正13年度 |
 |
85名 |
| 大正14年度 |
 |
81名 |
| 大正15年度 |
 |
85名 |
| 昭和2年度 |
 |
97名 |
| 昭和3年度 |
 |
2名 |
 |
| 姫路高等女子職業学校 |
| |
昭和3年度 |
 |
43名 |
 |
| 昭和4年度 |
 |
70名 |
| 昭和5年度 |
 |
78名 |
| 昭和6年度 |
 |
117名 |
| 昭和7年度 |
 |
116名 |
| 昭和8年度 |
 |
112名 |
| 昭和9年度 |
 |
106名 |
| 昭和10年度 |
 |
79名 |
| 昭和11年度 |
 |
73名 |
| 昭和12年度 |
 |
110名 |
| 昭和13年度 |
 |
148名 |
| 昭和14年度 |
 |
137名 |
| 昭和15年度 |
 |
148名 |
  |
|
